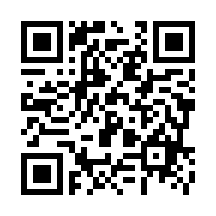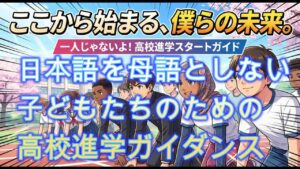Views: 319
2024年、在京外国人の子どもたちの都立高校進学は厳しい結果でした。
外国籍の生徒らを対象とした都立高校入試の「在京外国人生徒等対象選抜」(在京外国人枠)で、今春は前年の1.5倍にあたる245人が不合格となった。都は今年から募集人数を80人増やして240人としたが、来日する子どもが急増するなか、受け入れ態勢が追いついていない現状が浮き彫りになった。(朝日新聞2025年5月10日付記事より)
都教育委員会によると、都内の公立学校で日本語指導が必要な外国籍の児童・生徒は、2020年度の3796人から24年度には6036人と約1.6倍に増えた。なかでも小中学生は、3025人から5163人と増加が目立つ。都教委の担当者は「来日する外国籍の子どもが増えていて、そうした子の多くが在京枠を受検した可能性がある」とみている。
在京外国人枠入試は1989年度に始まった。英語か日本語の作文と面接で合否を判定。昨年度までは全日制8校160人だったが、今春からは新たに昼夜間の定時制4校を加えた計12校で240人を募集した。来日3年以内という制限があるが、今春から国籍要件が緩和され、日本国籍でも受けられるようになった。(参照 朝日新聞 5月10日付)
私達は、在留外国人の子どもたち支援のため昨年度は2回の進学ガイダンスを実施
この結果は、昨年度の外国人枠の入試においても100人こしの不合格者が出ていたことからも予想できました。
私たち、NPO法人全国国際教育協会は、昨年は、多文化共生、在留外国人の子どもたちの支援を充実するために、2回の進学ガイダンスを実施しました。
2回実施した進学ガイダンスは、今までに体験した先輩の話しなど体験談やアンケート結果など、詳細にまとめて報告しました。この報告は、都立高校を目指す、在留外国人の子どもたちが、何を考え、どのように努力してきたかがよくわかります。私達NPO法人全国国際教育協会は、経過をしっかり記録に残しながら、多文化共生社会を目指してこの支援活動を行っています。
在京外国人枠の受検とは何か?
ここでいう外国人枠をまとめると、下のような内容です(2024の内容で今年の内容が同じとは限りません。都教委に問い合わせてください。
国籍を問わず、日本語指導が必要な生徒が一定の応募資格を満たせば都立高校に受検できる入試です。
応募資格
年齢条件 日本の中学3年と同じ年齢以上 (誕生日が2010.4.1よりも前)
住所要件 全日制の学校を受検する場合は、都内に両親と同居する必要があります。定時制の学校を受検する場合は、本人の住所か勤務先が都内にある必要があります。
修学要件 (2024年の内容)
①国籍を問わず、現地校を修了見込み
②国籍を問わず、日本の中学校を卒業見込み
※入学日現在の在日期間が、3年以内の必要があります。
➂外国籍で、日本国内の外国人学校を修了見込み
検査内容
作文と面接です。言語にについては、それぞれの検査において日本語または英語を選ぶことができます。
このように、在留外国人の子どもたちにとっては、日本語という語学のハンデがあるわけで、日本人との競争となる、3教科、あるいは5教科の一般入試を受けるよりも、ハードルが下がり、安心して受検できるわけです。それだけに、在留外国人が増えて、その子供たちが増えれば、受検者の子どもたちも増ええてくるのは当然です。
ただし、この特別入試を実施する高校は、12校240名の枠だけなのです。
在京外国人生徒等対象の選抜を実施する都立高校(12校)
都立砂川高等学校
都立府中西高等学校
都立田柄高等学校
都立荻窪高等学校
都立杉並総合高等学校
都立国際高等学校
都立飛鳥高等学校
都立六郷工科高等学校
都立竹台高等学校
都立一橋高等学校
都立浅草高等学校
都立南葛飾高等学校
この12校は、他の都立高とどこが違うのか?
入学したあとも、日本語学習がカリキュラムに含まれます。在京外国人生徒の学習の場を様々な形で設けています。
例えば、学校として、多文化共生を唱え、在京外国人生徒の学校設定科目「日本語」の設置、取り出し授業、放課後および土曜講習を実施し、学習の場を確保し、日本語能力と基礎学力の向上を図っています。それは様々な文化的背景を持つ子どもたちと、交流ができることです。
しかし、このような日本語教育カリキュラムが、全部の都立高校にあるわけではないのです、
在京外国人生徒対象の選抜を実施する12校は、入学したあとも、日本語の勉強を、学校のカリキュラムの中で続けられるのです。もちろん、日本語の読み書きが堪能で、ハンデがない子にとっては、一般入試で好きな高校を選べますが、来日して、3年以内とすると、日本人と一緒の一般入試は、ハンデが大きいと感じるでしょう。
私たちは、昨年度の特徴として、3部制定時制が含まれたことに注目しました。
3部制定時制が含まれたことは大変大きいです。普通科の3部制定時制ですと、定時制は通常4年で卒業のところ、他部の授業をとることで、3年で卒業できます。特別枠の中に一橋、浅草、荻窪の3部制定時制3校が入ったことで、この3校を志望することで、今回は合格の可能性があがりました。この傾向が今年度も続くかはまだ予測できませんが、今回は新しい3部制という東京都独特のシステムの評価が、在京外国人の子どもたちにまだなじんでいないことから、倍率も低かったと考えられます。
通常、普通高校の二次募集の倍率は上がりますが、1倍を超えたのは、一橋の普通科2部だけです。しかし、外国人特別枠に入っている学校ですから、日本語に対する支援が校内で充実しています。
ただし、二次入試は、一般入試なので、国語、数学、英語の3教科その他面接や実技受検が入る高校もあります。国語は難易度が高いですが、数学、英語は中学で勉強していればそれほど難易度は高くないと思います。数学、英語で点数を取れれば、国語がダメでも、合計点で合格に持ち込めます。私たちグループは、元教師や校長経験者が多いので、相談してもらえれば、良いアドバイスをすることができます。
245人もの不合格者がでた問題の根源はどこにあるのか?
今後も、在留外国人は増えていくと考えれば、多文化共生の観点からも、すべての都立高校に、日本語補助の予算や人員が整い、校内での、日本語指導がカリキュラム上で充実されれば、都立高全体では十分な受け入れ能力はあります。現状募集が定員に満たない高校は多くあるわけです。しかし、働きかた改革すべき職場としてやり玉に挙がっている教育現場では、教員が多忙で対応できない現状も存在するのです。今できるのは、12校をさらに増やしていくか、各校20名の枠をさらに増やすことでしょう。
多文化共生は世界で活躍できる人材の育成にもつながり、日本人の子どもにもメリットがあります
教室に、外国にルーツを持つ子供が混在していることは、教室で、多文化共生の体験をすることができるメリットがあります。外国に留学しなくても、世界には多様な文化が存在することを体験できます。これからの子供たちには、自己を確立しつつ、他者を受容し、多様な価値観をもつ人々と協力・協働しながら課題を解決する力が求められます。多くの外国の人々と交流する機会が増えていく中、自らすすんで積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度も養われるのです。
クラウドファンディングサイトは、スマホからはこちらのQRコードで表示してください。PCからはFor Good!をクリックしてください。ご支援よろしくお願いします。
for Good クラウドファンディングQRコード