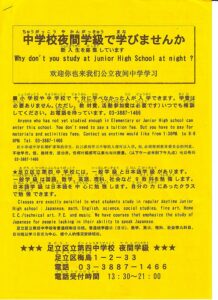Views: 945
DLAとは:Dialogic Language Assessment for Culturally and Linguistically Diverse Students
 外国人児童生徒の言語能力を測定する場合、日本語能力のレベルのみならず、年齢にともなう認知力の発達段階に考慮する必要があります。 日本語能力は、母語、年齢、入国年齢、滞在年数(四大要因)による影響を受けるので、これらを考慮した測定ツールが必要なります。
外国人児童生徒の言語能力を測定する場合、日本語能力のレベルのみならず、年齢にともなう認知力の発達段階に考慮する必要があります。 日本語能力は、母語、年齢、入国年齢、滞在年数(四大要因)による影響を受けるので、これらを考慮した測定ツールが必要なります。
文部科学省では、平成22年度から24年度にかけて「外国人児童生徒の総合的な学習支援事業」を実施し、そのひとつとして国立大学法人東京外国語大学に委託して「学校において利用可能な日本語能力の測定方法」の開発を行ってまいりました。数多くのモニター調査と学校や教育委員会でのヒアリングを重ね、児童生徒の日本語能力を把握するだけでなく、その後の指導方針を検討する際の参考にもなる資料が出てきました。
「DLA」を使用する際の基本的なステップ ・測定ツールを有効に使うには、次のステップを踏むことをお勧めします。
① 評価の目的を明確にする:「DLA」を使って、子どもたちのどのような側面、例えば、言語能力面であるのか、思考力などを必要とする認知面であるのか、具体的に知りたいことを明確にする。「DLA」から知りたい情報を確認する。
② 評価ツールを選ぶ:「DLA」で提示されたいくつかの評価ツールから、目的にかなったものを選ぶ。
③ 評価ツールを理解する:事前に評価ツールの実施方法をよく読み、進行方法を十分に理解しておく。
④ 子どもたちの力を最大限発揮させる:「DLA」の実施にあたっては、「DLA」<はじめの一歩>(詳細は後述)を通して、ラポール(共感できる信頼関係)を築き、持っている力を思う存分発揮できるよう配慮する。また、技能別テストが可能かどうかを判断する。
Dialogic Language Assessment for Culturally and Linguistically Diverse Students
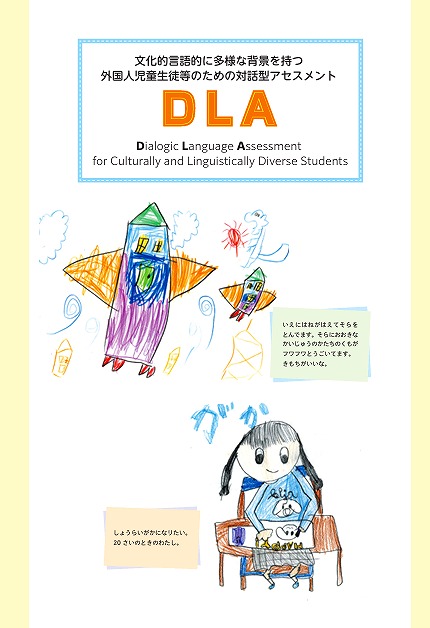
改訂版DLA外国人生徒児童等のためのことばの発達と習得のものさし
「ことばの力のものさし」
外国人指導生徒等の日本語の評価の方法が変わりました。
・複数言語での力(GPL)思考、判断、表現力を支える包括定な言葉の力(ステージ:認知)
・日本語固有(LSP)日本語固有の知識・技能・様態(ステップ)
の両方でDLAを見ていきます。
ポイント
Point1 一番早く伸びる「聞く・話す」力を最大限に活用
Point2 子供が持つすべてのことばの力を使って何ができるのかを捉える
*トランスランゲージング教育論
カミンズ「言語相互依存説」
Point3 学習指導計画の立案・見直しのためのアセスメント
Point4 子どもにとって学びの時間。「わかる」「できる」「楽しい」がやる気を引き出す
*‘ヴィゴツキー「発達の最近接領域ZPD」
変更点
・「JSL評価参照枠」の廃止→「ことばの力のものさし」で評価
・DLA〈書く〉と〈聴く〉を削除(〈書く〉一般教室内で見ていく)
DLA〈話す〉の名称をDLA〈話す・聞く〉に変更
・DLA〈はじめの1歩〉〈話す・聞く〉を多言語化(8か国)
・高校生にも応用できるようにDLA〈聞く・話す〉〈読む〉をナイナーチェンジ
資料
・「ことばの力のものさし」まるわかりガイド
https://www.mext.go.jp/content/20250620-mxt_kyokoku-000042836_01.pdf
・「ことばの力のものさし」実践ガイド
https://www.mext.go.jp/content/20250620-mxt_kyokoku-000042836_02.pdf
・youtube(旧DL
https://youtu.be/0fQAv2YWSCU?si=Enb6bUL7uzq1dKxr 初めの1歩
https://youtu.be/LuKBRft9f0s?si=lXpJGJEDeC_hsgsD 読む
https://youtu.be/CT1B_ZQFDFw?si=G9WJLOpOqIgUgo5Y 話す聞く
・DLAワンポイントレッスン動画⇒Plant全国教員研修プラットフォームからログイン
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413_00003.html
改訂版DLAを用いた海外につながりがある子供たちの日本語評価が東京都で始まりました。
7月に行われた中学校の評価に参加しました。
東京都でのDLA評価は去年から始まりました。
去年は学校も私たち実施者も初めてで時間に追われながらの作業でした。
今年はDLA実施2年目となりますが評価の方法が変わりましたし、都教委の担当の方も変わられていて去年にもましてバタバタでの開始となりました。
今回、実施者は経験者同士のペアだったのでゆとりをもって作業ができました。
改訂DLA研修は東京都の研修以外にも何回か受講しましたがステージの判定は母語話者の参加が不可欠だと感じています。
評価後学校、担当者にFBして日頃子供の様子をよく見ている先生とともに最終的に評価をすることになっていますが時間の関係で、評価の説明今後の対策の説明で終わってしまいました。
この評価がどのように活用され、子どもたちの日本語能力がどのように変化したか追跡調査が必要です。
私たち実施者へのFBもぜひお願いしたいと思います。
学校と実施日に実施者を見つけるのが大変そうです。私とのペアの方は予定を変更して参加されたそうです。次回は9月からとなります。
去年、今年の東京都DLA研修を受けた方 DLA実践に参加してみませんか。
日本語の能力が低い子どもたちは「やる気がない」「学習障害があるかもしれない」と判断されがちです。
子どもたちはまだ言葉で十分表現する力をもっていません。彼らは困難と闘って疲れているのかもしれません。
子どもたちの持っている力を有効に使えるようにするためには日本語教師だけではなく学校、担任、クラスメート、学校カウンセラー、ソーシャルワーカー、教育委員会、地域のボランティア教室などつながりが不可欠です。
子どもたちが学びを継続できるようにこれからも支援をしていこうと思います。
地域日本語教育コーディネーター(日本語教師) 斉藤 小郁